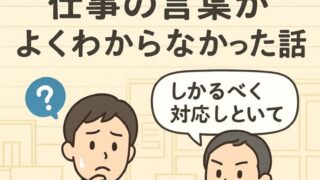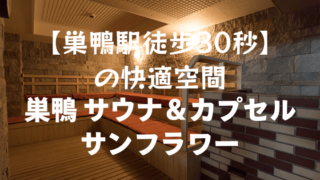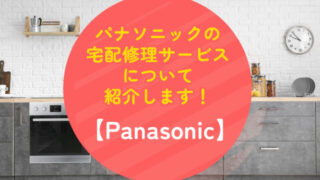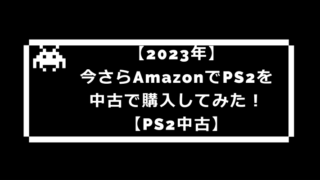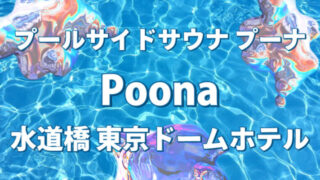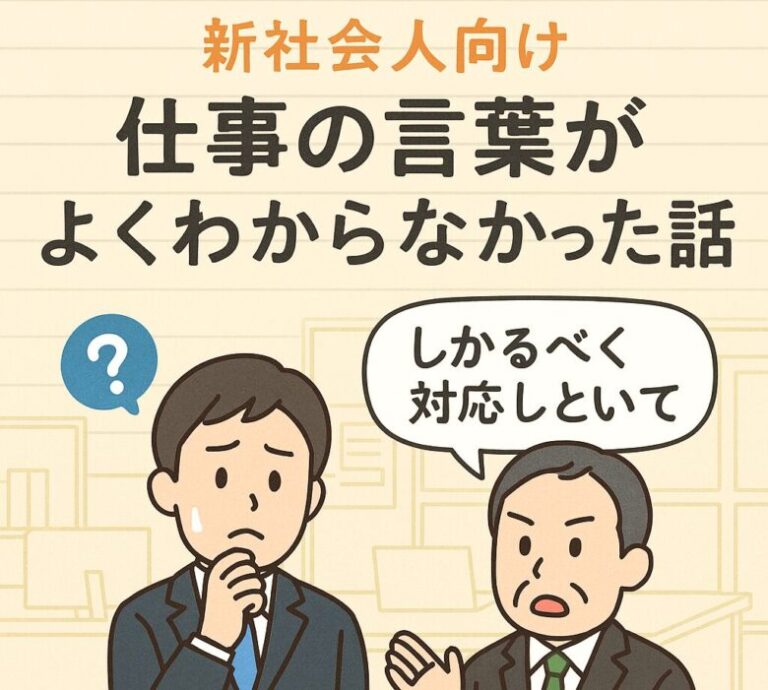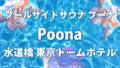目次
新年度、社会人デビューおめでとうございます!
こんにちは!今日はちょっと雑記です。
4月に入り、新社会人として働き始めた方も多い時期ですね🌸
私も昔はドキドキしながら社会人生活をスタートしたのを思い出します。
そんな中で意外と戸惑ったのが、「ビジネスの言葉、通じない問題」。
特に、上司や先輩が使う “おじさんビジネス用語” に最初は混乱しました…。
「しかるべく対応しておいて」って、つまりどうすればいいの?
社会人になってしばらくすると、こういう言葉に出会います:
- 「鉛筆なめなめして」
- 「いってこいだったね」
- 「一丁目一番地だから」
- そして、「しかるべく対応しておいて」
……え、どうすればいいの?😇
「JTC的」って文化、実はけっこう根強いです
こういう言い回しって、JTC(Japanese Traditional Company)と呼ばれるような、
いわゆる「昭和・平成初期の企業文化」が強い会社に多かったりします。
一見すると「わかりにくい」「曖昧」と感じるかもしれませんが、
実はその背景には「察する文化」や「空気を読む配慮」もあるんですよね。
🌱 新社会人時代に困ったリアルな話
私も新社会人のとき、上司に
「この件、しかるべく対応しといて」って言われて、
「(え、なにを? どこまで? いつまでに?)」と完全に固まりました。
結局自分の解釈で進めたら、「いやそうじゃないでしょ」と戻されて、
心の中で “しかるべく対応返し” したくなったのを今でも覚えてます(笑)
🎯 どう乗り切る?対処法いろいろ試しました
新卒1年目〜2年目くらいまで、いろいろ試してみて「これ効くかも」と思ったやつをシェアします👇
✅ 1. 「具体的にどうしたらいいか?」を聞き返す
フワッとした指示は、こちらから翻訳して聞き返すのが吉。
「A案とB案が考えられるんですが、どちらの方針がよさそうですか?」
→ 質問というより“確認”っぽく聞くのがコツ!
✅ 2. チャットやメモで“見える化”して確認
言われたことを自分なりにまとめて送ると、
相手も「そうそう、それ!」って返してくれたりします。
「今の話、〇〇さんに確認→資料作成→金曜までに提出、という流れで進めますね!」
✅ 3. 曖昧ワードを言い換えて返してみる
「泥臭くやる」→「訪問件数を増やすってことですか?」
「コンセンサス取って」→「〇〇さんと□□さんに確認すればOKですか?」
こっちが具体化して返すことで、相手も認識を整理できることがあります。
✅ 4. わからなかったら、素直に「確認」スタイルで聞いてみる
言い回しがちょっとピンとこなかったときは、
無理にわかったふりをせず、やわらかく確認するのが一番◎です。
例:「すみません、“一丁目一番地”って、最優先ってことで合ってますか?」
「“しかるべく対応”って、具体的には〇〇の対応で大丈夫ですか?」
相手を否定せず、素直に確認するスタイルなら、角も立たず、自然にやりとりできます👍
⚠️ 注意ポイント:気をつけたいこともあるよ
対処法を使うときに、私が気をつけてるのはこんなこと👇
🔸 聞き返しすぎると「細かい人」と思われるかも
→ 何でもかんでも「それってどういう意味ですか?」と聞くより、
選択肢を出して聞く or メモで確認するのがスマート!
🔸 指摘っぽくなると空気がピリッとしがち
たとえば、言い回しの意味がわからなかったときに、
そのまま「わかりません」「意味がよくわかりません」と言ってしまうと、
相手によってはちょっとピリッとしてしまうこともあります💦
そんなときは、
「すみません、〇〇ってつまりこういう意味ですか?」
「確認なんですが、△△って方向で進めればOKでしょうか?」
みたいに、確認ベースでやんわり聞くのが安心&スムーズです◎
🔸 曖昧さが必要なときもある
→ あえて曖昧にしてるとき(上からの指示をやんわり伝えてるとか)もあるので、
全部を明確にしすぎないほうがいい場面もあります。空気読む力、大事です…!
🔸 言い換えたつもりがズレてると逆に混乱
自分なりに「こういうことかな?」と解釈して言い換えてみたら、
実は相手の意図とズレてて、逆に混乱を招いちゃうこともあります。
例:「なるほど、“今後は現場主導で”って、もう上はノータッチってことですか?」
→「いやいや、そこまで割り切ってないから(笑)」みたいな感じに💦
なので、言い換えは“確認ベース”でやんわり伝えるのが安心です。
「つまり、現場側の意見を優先した方がよい、というイメージですか?」
こうすれば、相手も「そうそう、それ!」と返してくれる確率が高まります◎
💡 ちなみに:5W1Hを意識するとだいぶ楽になります
私は普段から、
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どうやって」(=5W1H)を意識して会話しています。
もちろん、毎回ぜんぶをフルで使う必要はありません。
でも、「何を」「いつまでに」「誰が」だけでも押さえておくと、
やり取りがスムーズになりやすいし、認識ズレも減らせる感覚があります◎
🎈 最後に:JTC的文化にも“よさ”はある
ここまで「曖昧で困った!」って話をしてきましたが、
実は、JTC的な言い回しにも 「いい面」 はあるなと最近は思うようになりました。
- 言葉をやわらかくして対立を避けたり
- 相手に判断を委ねてくれたり
- 人間関係の“丸さ”を保つための配慮だったり
ちょっと分かりづらいけど、相手を思いやる言葉でもあるんですよね。
だからこそ、受け手側としては「ちゃんとキャッチできる力」をつけたいなと思ってます!
🧭 まとめ:伝える力と、くみ取る力
新年度、仕事も人間関係も始まったばかりで不安も多いと思いますが、
少しずつ「会話のクセ」「社内のルール」みたいなものが分かってくると、
働きやすさもグッと変わってきます。
- 曖昧な言葉は“翻訳して返す”
- わかりづらいときは“確認ベースで聞く”
- 相手の意図を“汲み取ろうとする姿勢”を忘れない
このあたりを意識していけば、JTC的文化とも、うま〜く付き合っていけるはずです!
✍️ あとがき
というわけで、新社会人時代に戸惑った「おじさんビジネス用語」とその対処法でした!
慣れないことも多い時期だけど、無理せずゆっくりやっていきましょ。
同じように困ってる人のヒントになればうれしいです✨